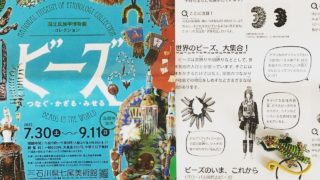はたき 作り方

細工物を作る時の副産物。着物の胴裏の使い道はないかと考えました。
私が小さい頃、母が作っていた桟ぱらい(はたき)を作ってみることにしました。30年以上ぶり。。。(笑)
胴裏は絹の羽二重生地なので、優しく埃をとってくれます。(あの頃は絹ではなく綿の端切れを利用していましたが。)
作り方は、生地を25mm幅に裂いて70枚ほど作ります。(大サイズです)
布を縦に裂くのは無理なので横に裂いていきます。竹の先にまとめてしっかりと結びます。結び方が甘いと、はたいている時にスポッと抜けてしまうので要注意。
しっかり結んだらくるっとひっくり返し、もう一度ギュッと結ぶ。で、出来上がり!
使う場所と用途に応じて、大きさは自由に変えることができます。机まわりならミニミニサイズで。。。 裂いた時の糸のもあもあになっている所は、邪魔な部分は切り落とします。その細い糸の断面で埃をとってくれます。静電気の作用もあるのかも?
布がくすんできたら、また新しく作り変えます。
はたきは、実家の方では「桟ぱらい」。ほかの地方では「ざいはらい」「さいはい」「ちりはらい」「さいはらい」「ぼんてん」「うちはらい」と様々な言い方があるようです。
もう、死語になりつつあるのかもしてませんが、使い勝手のいいエコなお掃除道具です。